
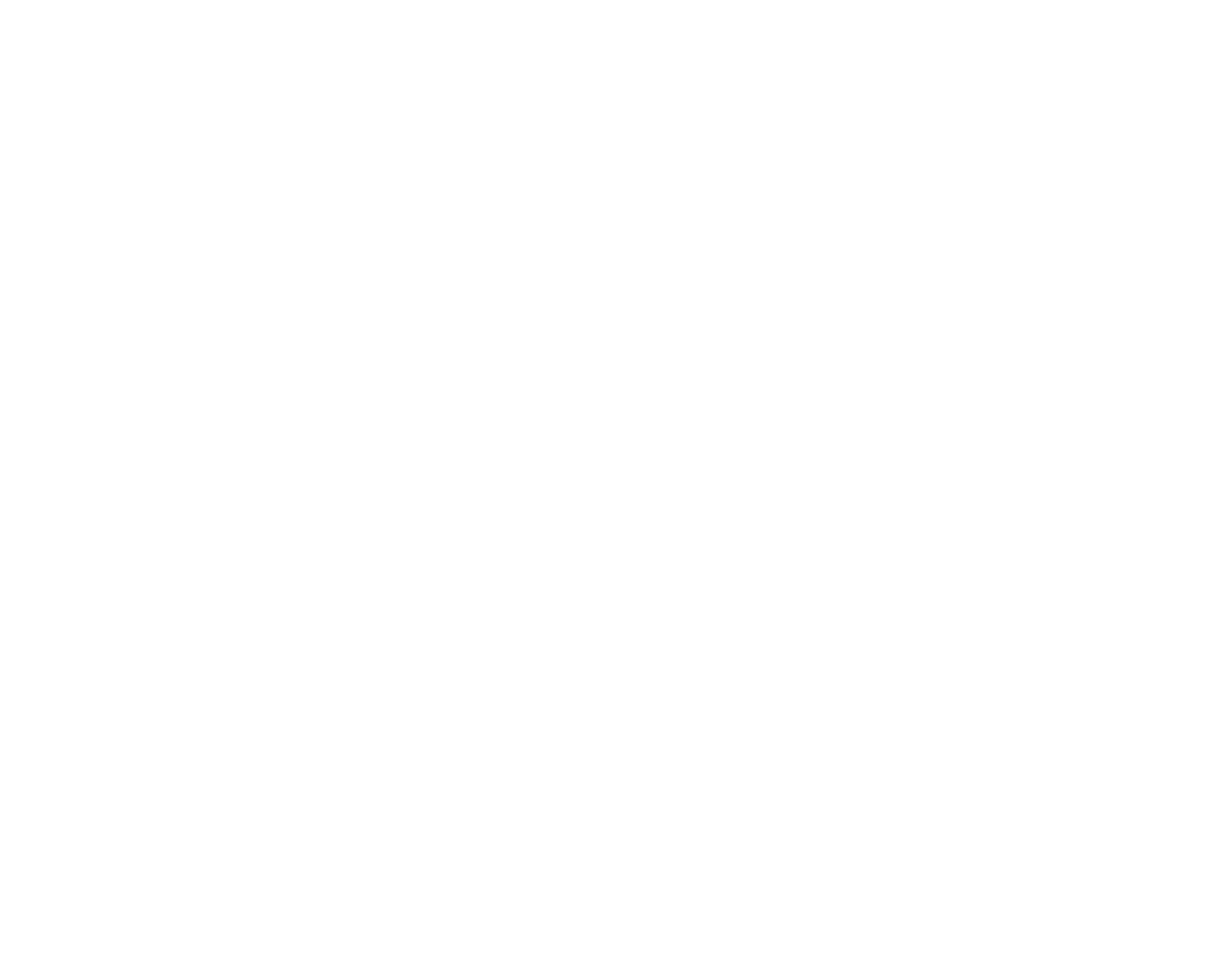
・自分のユニットを相手の天守閣に移動させ、防衛ユニットを撃破すると相手のライフが1減少。防衛ユニットがいない場合は、天守閣に移動されることでライフが1減少。天守閣に移動したユニットは、そのターンの終了時に元いた位置に戻ります。
・相手のライフ(全2)が全て尽きると、天守閣の陥落となり勝利となります。
・ライフ2つと、リソース3つを用意します。これは、数が分かれば何でも良いので、おはじきのような物でも、紙切れでもかまいません。紙に数をメモしていっても大丈夫です。
・デッキ40枚をしっかりと切って、カードを上から7枚引きます。
この時、土地カードが1枚も無いなど7枚の内容に不満があれば、2回まで7枚を引き直しが可能です(※特定の枚数だけを引き直すことはできません)。3回目からは1回の引き直しにつき、リソースを1消費します。
更なる救済措置として、最初のターンのみリソースを1つ消費して、デッキから好きな土地カードを1枚持ってきて、手札の中の1枚と交換ができます。交換した土地ではない方のカードをデッキに戻して切り直します。
・自軍の天守閣を好きなマスに配置します。
・ジャンケンをして勝った方が、先行か後攻か好きな方を選んでゲーム開始です。
・ターン毎にカードを1枚デッキから引き、基本リソース1を入手します。
・占領している土地の数だけ、年貢としてリソース1を追加で入手します。
※土地の上に平民や武将のユニットが召喚されている状態を「占領」と呼びます。ユニットが召喚されていれば、自軍の土地でも敵軍の土地でも「占領」の状態となります。
【例】土地2つを占領している場合
1(基本リソース)+2(追加リソース)=3リソース
・1ターンにつき1枚の土地カードを配置できます。土地カードは隣接する位置(斜めは除きます)にしか配置できません。つまり、天守閣に隣接しているところから広がっていく事になります。
配置した自軍の土地カードの上に、平民や武将カードを召喚することになるため、土地の配置が極めて重要になります。
・自軍の平民または武将が占領している土地は、自軍の土地・敵軍の土地に関わらず、手札にある土地と入れ替えることが可能です。入れ替えられた土地は、ゲームから除外されます。
・平民はウラ向き、武将は表向きで召喚します。
※武将をウラ向きで平民のコストで召喚し、それが発覚した場合、ルール違反として発覚した瞬間に敗北となります
・敵の領地への直接召喚は禁止ですが、敵陣の土地に移動することは可能です。
・「武将」「平民」の召喚、「どうぐ」の装備、「儀式」を行う、いずれも左上に記載されている数字だけ、リソースを消費します。
※平民の能力を使用する時や、神職ユニットが儀式を行う時は、カードを表向きにします
移動:「武将」と「平民」は、ユニットに隣接している土地への移動が可能です。上下左右へ移動はできますが、斜め方向への移動はできません。このフェイズ中にいずれかのユニットを1度だけ移動させる事ができます。
戦闘:移動先に敵ユニットがいる場合は、自軍のユニットと敵ユニットを同時にオープンして対決します。
・どうぐの装備や儀式は、「召喚フェイズ」か「行動フェイズ」に行います。どうぐの装備は、必ず戦闘を開始する前に装備してください。
・儀式はどのタイミングでも使用可能です。
・自分が攻撃側として戦闘が発生した時、土地の周囲1マス以内(斜めも含む)に自軍ユニットがいれば、いずれかのユニット1体のみを合流させて戦闘に加えることができます。
・合流したユニットの「攻撃力のみ」を攻撃しているユニットに加算します。すくみが発生する場合は、その数値を足した値を倍にします。
・挟撃に参加したユニットは戦闘終了後、牢屋へ送ります。
・「ターン終了」を宣言して、相手のターンに移行します。
この時に手札の枚数が8枚以上の時は、7枚になるように手札を捨ててからターンを移行します。
また、リソースが11個以上ある時は、10個になるようにリソースを捨てて、山札からカードを1枚引く。例えば、ターン終了時にリソースが15個ある場合、10個になるように5個リソースを捨てて、カードを1枚引いてからターンを終了する。
自軍の本陣となる土地で、ここが占領される(陥落)とゲーム敗北となります。40枚のデッキに必ず1枚入れる必要があります。
カードに記載されている能力は、自軍の領地内に敵のユニットが存在する場合、自分の好きなタイミングでターン毎に1度だけ使用することができます。
低コストで召喚可能な平民カードは、武将カードや儀式カードに比べて扱い易く、序盤から場に出して活用し易いのが特徴です。 このカードは、全てのカードが2コストで統一されており、安定した運用が可能です。召喚したターンは、移動や戦闘ができません(召喚酔い)。
戦闘に1度負けると牢屋送りとなります。
平民カードには個々に様々な能力が設定されていますが、その能力を使用するには、カードを表向きにしなければいけません。
【能力例:木こり、男】木の出荷:森林・林地を占領している場合、リソースを+1追加で算出する
※このユニットがウラ向きで土地を占領していても、リソースを得ることはできません。表向きにして土地を占領することで、初めてリソースを得ることができます。
デッキの中核となる強力なユニットで、戦況を一変させる特別な能力を備えています。戦闘や戦術の展開において重要な役割を果たし、このカードの扱いが勝利の鍵となります。ただし、召喚したターンは、行動ができません(召喚酔い)。
【能力例:細川忠興】自軍のユニットが戦闘に勝利するたび、リソースを1つ得る。このユニットが勝利した場合、自軍の他のユニット1体を1マス移動させて戦闘させてもよい。
ユニットの召喚・進行や儀式カードの効果を発動させるために必要で、このゲームの基盤となる重要なカードです。 後述の儀式カードのように一部のユニットは特定の土地とシナジーを持っています。
自軍の平民または武将が占領している土地は、自軍の土地・敵軍の土地に関わらず、手札にある土地と入れ替えることが可能です。入れ替えられた土地は、ゲームから除外されます。
平民や武将に装備させることで様々な効果を発揮するカード。ユニットの攻撃を補助するものから、儀式の発動を手助けするものまで、その効果は多岐にわたります。
このカードには戦闘中に1度使用して牢屋へ送る「戦闘どうぐ」と、ユニットに装備して使用し続ける「装備どうぐ」の2種類のどうぐがあります。装備どうぐは1キャラにつき1つです(ただし、宮本武蔵などの能力での複数装備は、その限りではありません)。
【効果例:天照の軟膏(戦闘どうぐ)】使用ユニットの傷カウンターを1つ除去する。除去したなら『こうげき+1』『ぼうぎょ+1』
【効果例:腹当(装備どうぐ)】このユニットが土地と適合し、能力を発揮できる場合、。さらに『ぼうぎょ+2』
特定の条件を満たすことで発動が可能となり、ゲームの流れを一変させるほどの強力な効果を持つ特殊なカードです。 カードの左上に「信仰のシンボル」が付いている「信仰の土地」と「神職ユニット」が必要となり、「信仰の土地」の上に「神職ユニット」がいる場合にのみ、このカードを使用することができます。
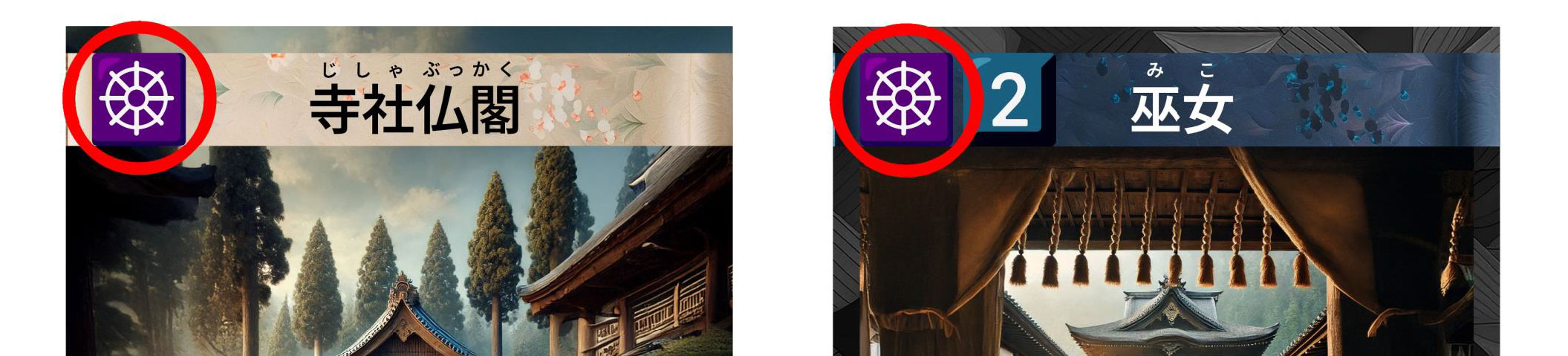
すべての土地から1つの土地を選び、その土地とその土地に存在するユニットをゲームから除外します。
・ユニット同士の戦闘は、カードの左半分に記載されている数値の大小によって勝敗が決まります。 戦闘開始時にカードが伏せられていた場合、戦国時代の鬨の声に習って「エイ」「エイ」「オウ」の掛け声でカードをめくります。 どうぐを装備させたい場合は、掛け声の前に装備させます。
戦闘は、ユニットの左端に記載されている「ぼうぎょ」と「こうげき」の数字の大小によって勝敗が決まります。
【攻撃側】
・勝利:土地を占領します。
・敗北:ユニットを元の場所へ戻します。
【防御側】
・勝利:土地を占領したままです。
・敗北:ユニットを牢屋へ送ります。
・武将と平民は、各ユニット毎に様々な能力を備えています。その能力の使い方が、戦況に大きく影響してきます。
・平民が相手本陣(天守閣)ラインに到達した時、もしくは平民が天守閣のライフを1減らした時。
・手札に武将カードがある場合、任意の武将を選んで平民を変身させます(=成る)。手札に武将カードがない場合は、デッキから1枚ずつカードをめくっていき、最初に現れた武将カードに成り、デッキを切ります。手札にある武将を召喚するか、山から1枚ずつめくっていくか、どちらの方法で武将を召喚してもかまいません。
武将は、成る前の平民の上に置いて使用します。

低コストの平民で早期に移動し、手数の多さで相手の天守閣の陥落を狙うか、リソースを蓄えて武将を召喚し、圧倒的な攻撃力をもって場を制圧し天守閣を陥落するか、移動のタイミングは人それぞれです。
・心理戦平民は基本的に裏返しで召喚されるので、相手ユニットの攻撃力と防御力を予想して、それに対する自軍ユニットの攻撃力と防御力を鑑みて、相手を攻撃するかどうか、どうぐを使用するかどうかなど、思考を張り巡らせる心理戦を体験できます。
・デッキ構築各武将のテーマに沿ったスターターデッキそのままでもプレイは可能ですが、別のスターターデッキなどからカードを追加し、各カードの枚数を自分自身で調整して自分だけのオリジナルのデッキを構築することで、多様な戦術が可能となります。プレイヤーの数だけデッキがあると言っても過言ではありません。
「武将隊戦棋 成る!」に登場するカードの一覧を、こちらからご覧いただけます。
また、2025年6月7日に発売されたブースターパックに初登場したカードの一覧を、こちらからご覧いただけます。
「武将隊戦棋 成る!」についてのお問い合わせは、
こちらまでお願い致します。
【株式会社ヤマワキ】
〒725-0003 広島県竹原市新庄町29番地
担当:森川・折元
営業日/月曜日~金曜日(祝日を除く)
営業時間/8:30〜12:00、13:00~17:15